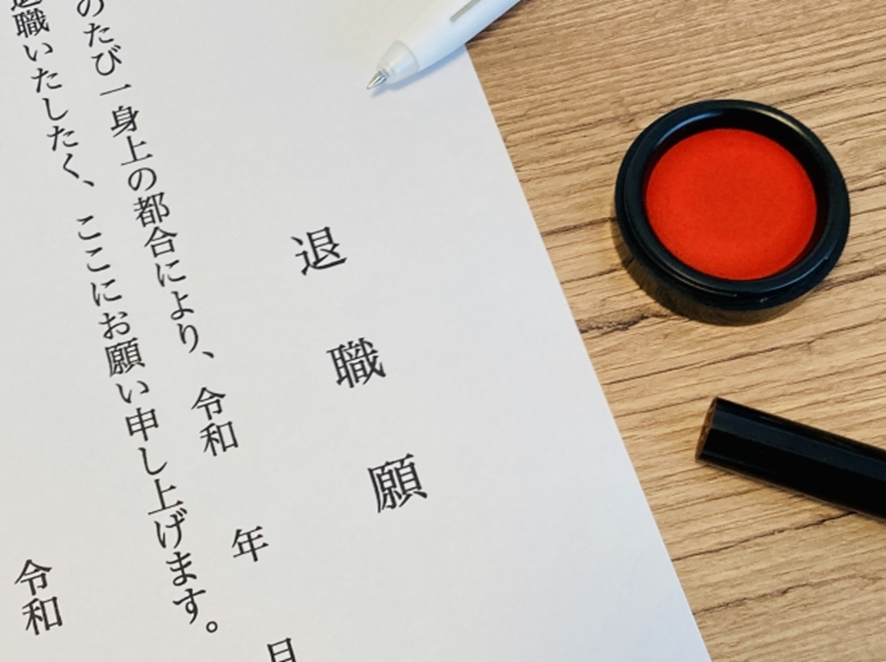円満退職は、会社、従業員の双方が納得した上で退職の手続きをすることを言います。円満退職をすることは今までお世話になった会社や同僚、上司に対していい印象を残すだけでなく、転職活動や次の転職先に対しても影響を与えます。しかし円満退職という言葉がある通り、円満でなく、退職の際にもめてしまうこともあります。
円満退職をするためには、会社との良好な関係を維持しながら、プロフェッショナルとしての信頼性と誠実さを示すことが鍵となります。事前の十分な準備、上司や同僚への丁寧な意思伝達、そして細やかな業務引き継ぎが成功の要となります。退職プロセスを慎重に、かつ誠実に進めることで、将来の職業人生においても良好なネットワークと評判を築くことができるでしょう。
以下に、円満退職を実現するための具体的な方法とポイントをまとめます。退職の事前準備、退職の意思の伝え方、引き継ぎ方法、そしてよくあるトラブルと解消法をお伝えします。

目次
1.退職の事前準備と心構え
退職の決意を固める
円満退職を成功させるためには、まず自身の退職の意思を明確にし、冷静に判断することが重要です。以下のポイントを慎重に検討しましょう。これらの軸がしっかりとしていると、退職の意思を示した後に起こりうる、引き止めにあった際も、冷静に、会社側が納得できるような説得をすることができます。退職を考えていたが、これらを考えると今のままでもいいのではないかと思うこともあるかもしれません。自身のキャリアの棚卸をしつつ、以下の点を重点的に考えていくとよいでしょう。
- キャリアプランとの整合性
- 現在の仕事や職場環境に対する思い、退職の本当の理由
- 次のキャリアステップへの展望
- 経済的な準備状況
退職理由の整理
退職の理由を明確かつ建設的に整理することが大切です。理由は、後ろ向きなものや会社の批判になるようなものは避けるからです。印象が悪くなるだけでなく、引き止められる原因にもなってしまいます。円満な退職を目指すためにも、前向きで応援されるような理由になるように考える必要があります。以下のような観点から自分の退職理由を棚卸して、説明できるようにしておきましょう。
- キャリア成長の機会
- ワークライフバランス
- スキルアップの必要性
- 新たな挑戦への意欲
〉気を付けたいポイント
退職を決意するに至る多くの場合、現在の職場に対するネガティブな思いもあるかと思います。しかしその本音をそのまま伝えることは、避けましょう。本音はあるとしても前向きな理由に転換していくことで、転職先への転職理由、そして現在の職場に伝える退職理由も、受け入れられやすいものとなります。
実際には、給与が低い、人間関係が悪いというのが、退職の理由の上位として挙げられます。しかしそれをそのまま伝えてしまうと、給与を上げるから残ってほしい、配置転換を検討するので…と打診されることになり、断りづらくなることもあります。
例えば業務で関わった興味をもった分野をより深めていきたい、これまでの経験を生かして、新しい環境で挑戦していきたい、より専門性を高めるために勉強をしたいなど、本音に近い形で、納得してもらえるような建前の理由を用意する必要もあります。
また、退職した後に新たな勤務先に転職する人も多いと思います。転職の際は、まず内定先企業から「労働条件通知書」「雇入通知書」を提示してもらい、雇用条件を明確にすることが重要です。条件を事前にすり合わせておくと、後から「思っていたものと違った」というリスクを避けることができます。
2.上司・人事との円滑なコミュニケーション
事前相談と告知のタイミング
退職を決意したら、なるべく早めに伝えることが重要です。落ち着いた場所で、直属の上司に、対面で伝えます。決して、メールやラインなどで伝えることがないようにしましょう。慎重かつ丁寧に行う必要があります。以下の手順を参考にしてください。
直属の上司との1対1の面談を設定する
- 退職の意向を冷静に、感謝の気持ちとともに伝える
- 退職時期、引継ぎや業務の継続性について具体的な提案をする
- 退職後も良好な関係を維持したい意思を示す
退職面談での対応ポイント
退職面談では、前向きで建設的な態度を心がけましょう。引き止められたり、批判的なことを言われたりすることもあるかもしれません。それでも、自分のペースを保ち、淡々と、感情的にならずに事実ベースで伝えることが大切です。以下のことを心がけるとよいでしょう。
- 感情的にならない
- 具体的で明確な説明を心がける
- 会社や同僚への感謝の気持ちを伝える
- 建設的なフィードバックを提供する
〉気を付けたいポイント
転職先が決まっても、会社の事情を考慮せずに突然退職するのは避けるべきです。遅くとも退職の2ヶ月前には、直属の上司に退職の意思を明確に伝え、退職日について相談しましょう。会社によっては雇用条件で退職に関する規定がある場合もあるため、事前に確認が必要です。一方的に自分の事情ばかりを押し付けるのは、今までお世話になった会社に迷惑をかけてしまうことになります。
退職を伝える際は、必ず直属の上司に直接報告し、相手の立場を考慮したコミュニケーションを心がけることが円満退職の鍵となります。プロフェッショナルで冷静な態度を保ち、会社への感謝の気持ちを示すことが重要です。安易に同僚に話してしまったり、直属の上司を飛び越えて、その上の上司に伝えてしまったりすることはトラブルの元です。避けるようにしましょう。また、退職理由に関しても、上司に対しては建前の理由を、同僚には本音の理由を伝えてしまうと、思わぬところから情報が洩れてしまうこともあります。一貫した態度で、退職までもっていくことが円満退職の秘訣ともいえます。
3.円滑な引継ぎのために
退職の際に大切なのは引継ぎです。自分が行っていた業務を後任に引き継ぎ、自身の退職後も今までの業務が滞りなく進むようにするのが目的です。お世話になった会社、同僚そして取引先が困ることなく円滑にその後の業務が進むことを忘れずに進めていく必要があります。具体的には、自身の退職の数日前に完了するように、逆算して考えると、何か突発的な事態が起きた時も慌てずにすみます。
引継ぎ計画の作成
スムーズな業務引継ぎは、円満退職の重要な要素です。以下の点に注意して引継ぎを行いましょう
- 現在担当している業務の詳細な洗い出し
- 進行中のプロジェクトの状況整理
- 業務マニュアルや関連文書の準備
- 顧客や取引先との関係性の引継ぎ
具体的な引継ぎ方法
効果的な引継ぎのために、以下の方法を実践してください:
- 詳細な引継ぎ資料の作成
- 後任者との直接的な引継ぎミーティング
- 重要な情報や知識の共有
- 質問対応のための一定期間の対応可能性の提示
〉気を付けたいポイント
引き継ぎの理想は、後任者が一連の業務に慣れるまで見届けられること。そのためには、かなり余裕のある引継ぎ計画が必要です。自分の退職日から逆算してスケジュールを組んでいく必要があります。一般的に内定から入社まで1~2か月程度あると言われています。その期間で充分な引継ぎができるのか、現在の勤務先としっかりと確認して、会社の意向に沿うことも大切です。また、転職先からできるだけ早く来てほしいという要望を受けることもあります。すると、現在の職場の引継ぎどころか、後任者の採用や決定ができておらず、トラブルになることもあります。この場合は、双方に、なぜその期間が必要なのかということを確認して、お互いの落としどころを調整していく必要があります。
いずれにしても、引継ぎをほとんどせずに転職して、現在の職場の人達に迷惑をかけるようなことはないようにしましょう。まさに立つ鳥跡を濁さずを目指せるといいですね。

退職時にトラブルになりやすいことと、対処方法
退職は、労働者と企業の双方にとって重要な転機です。多くの感情的、法的、実務的な側面を含むプロセスがあるため、トラブルになることも多くあります。最も頻繁に発生するのは、退職の引き止めと有給休暇の取得に関する問題です。
労働者は、自身のキャリアを自由に選択する権利を持ち、使用者は従業員の意思を尊重する法的、倫理的義務があります。退職の引き止めや有給休暇の不当な制限は、労働基準法に基づき違法となる可能性があり、労働者の権利を侵害する行為と見なされる可能性があります。
ただし、はじめから権利だからと、主張をしてしまうと、円満退職からは遠のいてしまいます。まずは現在の勤務先に都合を確認しながら、転職先との兼ね合いを調整していくことが求められます。
1. 退職の引き止めについて
退職の意思を示したものの、引き止めに合い、なかなか退職日が決まらない。転職先の
就業開始日が迫っているのに困ってしまったという例は多くあります。
退職の引き止めは、法的には不可能です。以下のことを知識としてもっておくことで、万が一、執拗な引き止めに合った場合、冷静に対応できるかと思います。
- 退職の意思を伝えた後、会社が過度な説得や心理的なプレッシャーをかけることは違法になる可能性があります。従業員には退職する自由があり、会社はそれを受け入れる義務があります。
- 引き止めが執拗で、精神的な苦痛を与えるような場合は、パワハラや嫌がらせに該当する可能性もあります。
対処法:
- 退職の意思を明確に、かつ冷静に伝える
- まずは直属の上司に、そこで難しければその上の上司、人事部に相談をする
- 過度な説得や圧力を感じた場合は、労働基準監督署に相談する
〉気を付けたいポイント
退職に対して聞く耳をもってもらえない、退職届を破られるなどという話も聞きます。退職者を出すことが、上司にとってのマイナスの評価になるために、受理したくないということもあります。ただし、退職届が受理されなくても、退職はできます。法的には退職日の2週間前に退職の意思を示すことで、退職が可能です。しかしそれは最終的な手段として、まずは円満に退職ができるように、前向きな退職理由を棚卸して、冷静に伝えるようにしましょう。そしてまずは直属の上司、そしてそこでこじれてしまったら、その上の上司、人事部といったように段階を踏んで伝えていくようにしましょう。
2.退職時の有給休暇の取得について
退職前の有給休暇をすべて取得することは、実際には難しく、多くの人が、結局すべては消化できないままに退職の日を迎えるということになってしまいます。また退職前だから…と遠慮してしまうケースもあります。しかし有給休暇の取得は労働者の権利であり、同時に会社には従業員がその権利を行使できるよう保障する法的義務があります。退職を控えているからといって、この権利が制限されるわけではありません。むしろ、長期間働いてきた労働者の労をねぎらい、最後まで尊重する機会でもあるのです。
ここでは、有給休暇の定義、退職前に有給休暇を消化するためのコツをお伝えします。

有給休暇とは、従業員の権利であり義務
そもそも有給休暇は、正式には年次有給休暇という名称があります。年次有給休暇とは、入社より一定期間たった社員に対して、疲労の回復、ゆとりある生活の保障を目的として付与される休暇制度です。付与された日数は、仕事を休んでも給与を与えられ、減給されることはありません。
また2019年4月から労働基準法の改正により、すべての企業で年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員は、そのうちの5日についてはその年に必ず消化させることが義務付けられました。
確実に有給休暇を消化するためには
有給休暇を消化するためには、事前のスケジューリングが大切です。退職日を基準に逆算し、十分な引き継ぎ期間を確保することが重要です。会社と事前に綿密な調整を行い、業務の継続性を担保しつつ、自身の有給休暇取得の権利も確実に行使できるよう、戦略的に計画を立てることが求められます。以下に具体的なポイントをお伝えします。
有休消化のために必要な段取り
有給休暇を消化するためには、現在の会社と転職先、2つの会社と日程を調整する必要があります。円満退職のためには、双方の会社から不満がでることなく調整をしていくことが大切です。
- 転職先ですべきこと
有休消化期間を踏まえて、入社日を調整する
当たり前のことに聞こえるかもしれませんが、有給消化を考えて、入社日を設定する必要があります。というのも、勤続年数が長くなると、繰り越し分を含めて、最大で40日間の有給が付与されています。そのすべてを消化するとなると、約2か月程度かかります。内定をもらってから1~2カ月後に入社となることが多いので、すべての有給休暇を消化するなら、最終面接で伝える希望入社日を検討する必要があります。
- 現在の会社ですべきこと
有給休暇の残日数を確認、引き継ぎ期間を計算する
まずは正確な有給休暇の残日数を確認します。人事部に問い合わせたり、給与明細を確認したりすると、正確な日数がわかります。そして引き継ぎに必要な日数を計算します。それを踏まえて、有給休暇の申請計画を立てていきます。
また知っておくべきこととしては、有給休暇は、労働者に与えられた権利なので従業員が消化をしたいと言えば、基本的には雇用主側は断れません。従業員がこの日に有給を取得したいと申請することを時季指定権といいます。それに対して企業側は時季変更権という、権利をもっています。これは、業務のスムーズな遂行ができないという理由で、企業側が従業員に有給休暇取得の時季の変更を依頼することができる権利です。ただし、退職時は原則として時季変更できず、繁忙期であっても従業員の希望通りに有給休暇を承認することになっています。
有給休暇の取得パターンを考える
有給休暇の消化パターンには、主に2つの方法があります。最終出社をする前にすべての有給を使い切るパターンと、最終出社をしてから、残りの有給を使い切って退職日を迎えるパターンです。どちらもメリットデメリットがあるので、現在の職場、そして転職後の予定を鑑みて決めるとよいでしょう。
- 最終出社日の前に有給休暇を消化するパターン
特徴:
- 最終出社日の前に有給休暇を全て消化
- 業務引き継ぎは有給休暇開始前または消化期間終了後に実施
- 引き継ぎ相手とスケジュールを事前に明確に周知することが重要
メリット:
- 最終日に健康保険証や社員証を直接返却できる
- 有給前に引き継ぎを行うことを前提とするが、有給後にも勤務日があるので余裕がある。
- 最終出社日の後に有給休暇を消化するパターン
特徴:
- 最終出社日と退職日が異なる
- 最終出社日の翌日から有給休暇消化
- 有給休暇終了と同時に退職するこちらのパターンが一般的
メリット:
- 有給消化後に出社の必要がないので、リフレッシュや転職後の準備に充てられる
- 有給消化中も会社の健康保険が使用できる
〉気を付けたいポイント
有給休暇は社員に与えられた権利です。それでも会社が認めない場合は、人事部や上司の上長に相談しましょう。解決できない場合は、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。今は直接訪問だけでなく、電話やメールでの問い合わせに応じてくれることもあります。
また有給消化については買い取り制度を行っている会社もあります。雇用規定を確認してみるとよいでしょう。
実際に有給取得を考えると、退職日を超えてしまうというケースもよくあります。転職先が決まっている場合、転職先の入社した後も有給消化して、退職するということもあり得るかと思います。この場合は、双方の会社が二重就業を許可しているかを確認する必要があります。最悪の場合、退職する会社からの退職金の減額や、転職先での注意、内定取り消し、試用期間での解雇もあり得ます。

まとめ
円満退職のポイントとよく起こるトラブルについて解説しました。円満退職は、雇用主、従業員の双方が納得して、次に進むことが大前提となっています。今までの感謝の気持ちをもち、気持ちよく次に選んだ道に送り出してもらえるよう、計画的に進めていけるといいですね。またトラブルの事例でもお伝えしましたが、自分の権利と会社側の事情の板挟みになることもあり得ます。その場合は、自分の権利を優先するのか、今までの感謝の気持ちを表すために会社側の事情に譲歩するのかなど、自分の譲れない部分をもっておくと、いざとなった時に迷わずに進めていくことができます。退職という仕事人生の大きな節目、感謝の気持ちと未来への希望をもって進めるといいですね。
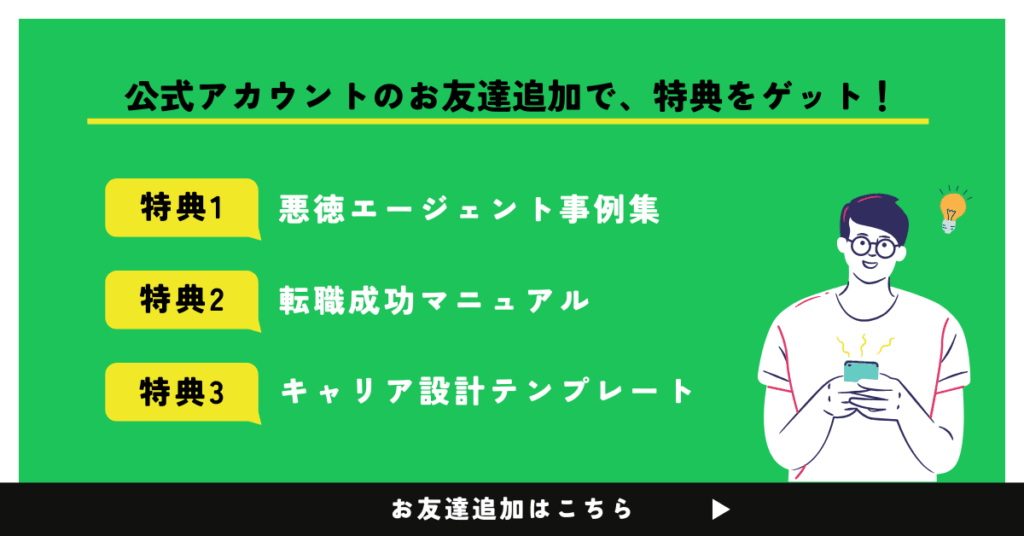
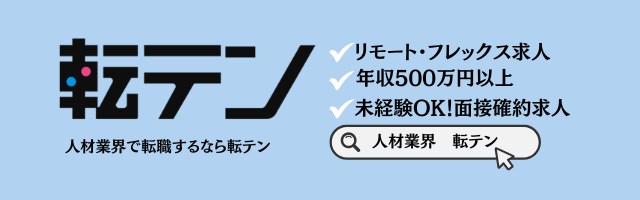

キャリアアドバイザー、リクルーティングアドバイザー、社内人事などを経て、現在は転職メディア「転テン」の運営を担当。転職に悩む方の力になるべく、リアルな現場経験を活かしたノウハウを発信中。あなたの「キャリアづくり」を応援します。
 コンテンツへ移動
コンテンツへ移動