人材紹介業での起業を検討している方にとって、厚生労働省の許可取得は避けて通れない道です。2025年の法改正で新たなルールが追加されており、準備不足のまま事業を始めてしまうと深刻な問題を抱えることになりかねません。
無許可営業は刑事罰の対象となるため、正しい知識を身につけることが何より大切になってきます。
この記事では許可取得に必要な5つの要件から具体的な申請プロセス、実際によくある失敗パターンまで実務的な観点からお伝えしていきます。
目次
人材紹介業に免許が必要な理由と法的根拠

人材紹介業は求職者の人生を大きく左右する責任の重い事業です。職業安定法によって厚生労働大臣の許可が必要とされているのは、労働者を守り、健全な労働市場を維持するためです。
「人を紹介するだけでしょ?」と軽く考えてしまいがちですが、実際には大量の個人情報を扱い、求職者の将来に直接関わる重要な業務を担うことになります。
有料職業紹介事業とは
有料職業紹介事業は、求人企業と求職者の雇用関係成立をサポートし、その対価として手数料や報酬を受け取る事業形態です。転職エージェントや人材紹介会社といった名称で運営されているサービスの多くがこれに該当します。
求職者の履歴書や職歴といった機密性の高い個人情報を大量に取り扱うため、個人情報保護法に基づく厳格な管理体制が求められています。
民間企業が営利目的で運営する人材紹介サービスは基本的にこの有料職業紹介事業に分類されており、手数料収入を得て職業紹介を行うことが特徴です。
人材紹介業の歴史について詳しく知りたい方は、こちらの記事で詳細な背景をご確認いただけます。
人材紹介業の歴史とは?江戸時代から現代まで100年の変遷と未来展望を徹底解説
有料職業紹介事業と無料職業紹介事業との違い
両者の最も大きな違いは、手数料や報酬を受け取るかどうかという点です。
| 区分 | 運営主体 | 代表的な事業者 |
| 有料職業紹介事業 | 民間企業 | 転職エージェント、人材紹介会社 |
| 無料職業紹介事業 | 公共機関、非営利団体 | ハローワーク、大学キャリアセンター |
ハローワークや大学のキャリアセンターは無料職業紹介に分類され、公共の利益を重視して無償でサービスを提供しています。
一方、民間の人材紹介会社は紹介成功時に企業から手数料を受け取る有料職業紹介事業として運営されており、そのため、より厳しい許可要件をクリアする必要があります。
免許なしで営業した場合の罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
職業安定法第64条では、無許可で有料職業紹介事業を行った場合の罰則として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。この処罰は法人の代表者個人に科せられるため、会社だけでなく経営者自身が刑事責任を問われることになります。
法的な処罰以外にも、無許可営業が発覚すれば社会的信用の失墜は避けられません。取引先企業との契約解除や事業継続の困難といった深刻な経営リスクが生じるほか、求職者や求人企業からの損害賠償請求を受ける可能性もあります。
人材紹介免許の5つの取得要件【2025年法改正対応】

人材紹介免許を取得するには、厚生労働省が定める5つの要件をすべて満たす必要があります。2025年の法改正では適正な運営に関する要件が強化され、特に転職勧奨の禁止期間とお祝い金支給の制限が新たに追加されました。
| 要件項目 | 主な内容 | 2025年改正点 |
| 職業紹介責任者 | 各事業所に1名以上専任配置 | 変更なし |
| 財産的基礎 | 純資産500万円以上、現金150万円以上 | 変更なし |
| 個人情報保護 | 適正な管理体制の整備 | セキュリティ要件強化 |
| 事業所 | 20㎡以上、独立性確保 | 構造要件の明確化 |
| 適正な運営 | 法令遵守、転職勧奨禁止 | 転職勧奨2年間禁止、お祝い金制限 |
職業紹介責任者に関する要件
各事業所に1名以上の職業紹介責任者を専任で配置することが義務づけられており、3年以上の職業経験と厚生労働省指定の講習受講が条件となっています。この責任者は法令遵守、業務運営の適正化、苦情処理、労働局との連絡調整といった重要な役割を担います。
また、職業紹介責任者は他の職業紹介事業者との兼任が禁止されており、当該事業所での専任が大前提です。3年以上の職業経験については、人事労務、営業、企画といった幅広い業務が対象となりますが、アルバイトや短期間の勤務は算入されないので注意が必要です。
責任者は職業紹介業務全般に対する責任を負うポジションなので、法的知識と実務経験の両方が求められる重要な存在といえます。
財産的基礎に関する要件
資産総額から負債を控除した額が500万円以上(事業所数分)、現金・預貯金150万円以上(事業所増加で60万円加算)という条件をクリアする必要があります。この要件は事業の継続性と安定性を確保するために設けられており、事業所数に応じて必要額が増加する仕組みです。
負債として計上される項目には、銀行借入、買掛金、未払金などが含まれ、これらを差し引いた純資産が500万円以上である必要があります。
財産要件の証明には、決算書や残高証明書といった公的な書類の提出が求められます。
個人情報保護に関する要件
求職者の個人情報を適正に管理する体制整備も必要です。システム管理・物理的セキュリティ・アクセス権限設定といった包括的な対応が求められます。具体的には、鍵付き保管庫の設置、入退室管理、職員への定期的な教育実施などが必要です。
個人情報保護法の改正により、セキュリティ要件がより厳格になっており、漏洩防止のための技術的・組織的な安全管理措置の実施が義務付けられています。
また、個人情報の取得時には利用目的の明示、本人同意の取得、第三者提供時の同意確認など、適切な手続きを踏むことも重要です。これらの管理体制については申請時に詳細な説明書類の提出が求められるため、事前にしっかりとした準備が必要になります。
事業所に関する要件
20㎡以上の面積(現在は緩和措置あり)、事務所用途、独立性確保、個人情報保護に配慮した構造が必要とされています。プライバシーに配慮した面談スペース、他法人との同居禁止、風俗営業地域での開設禁止といった注意点もあります。
事業所の面積要件は以前より緩和されていますが、適切な業務運営ができる十分なスペースの確保は変わらず求められています。独立性の確保では、他の法人や個人事業主との同一事業所での運営は原則として認められません。
適正な運営に関する要件
2025年1月施行の新規制として、紹介成功者への2年間の転職勧奨禁止と過度なお祝い金支給禁止が詳細に規定されました。この改正により、人材紹介事業者は紹介先企業に就職した求職者に対して、2年間は転職の勧奨を行うことが禁止されています。
お祝い金についても、過度な金額の支給は適正な職業選択を阻害する恐れがあるとして制限が設けられました。手数料表の作成では、求人者から受け取る手数料の上限や計算方法を明確に定める必要があります。
また、国外職業紹介を行う場合は、相手国の法制度への対応、現地との連絡体制の整備など特別な要件が追加されます。事業運営の基本的な方針に関わってくるため、申請前に十分な検討と準備を行うことが必要です。
人材紹介免許の取得費用と必要な手数料

人材紹介免許の取得には、申請手数料と登録免許税を合わせて最低14万円の費用が必要です。これに加えて職業紹介責任者講習費用、オフィス準備費用、法人設立費用(法人の場合)などが発生するため、総額では50万円から100万円程度の初期費用を見込んでおく必要があります。
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
| 申請手数料 | 5万円+追加事業所分 | 事業所数により変動 |
| 登録免許税 | 9万円 | 固定額 |
| 職業紹介責任者講習 | 8,800円~13,000円 | 実施団体により異なる |
| 法人設立費用 | 10万円~30万円 | 代行依頼時は高額 |
これらの費用は事業開始前に発生するものなので、事業計画に組み込んだ資金調達が不可欠です。
申請手数料と登録免許税:合計14万円
申請手数料は基本額5万円に加えて、2つ目以降の事業所については1万8千円が追加されます。登録免許税は事業所数に関わらず一律9万円となっています。申請手数料は収入印紙で支払う必要があり、申請書類に貼付して提出します。
登録免許税は許可証の発行時に必要となる税金で、法務局で収入印紙を購入して納付することになります。これらの費用は許可が下りなかった場合でも返還されないため、申請前の要件確認が何より重要です。
職業紹介責任者講習費用:8,800円~13,000円
全国民営職業紹介事業協会や日本人材紹介事業協会が実施する講習の受講費用について説明します。団体によって若干費用が異なりますが、おおむね8,800円から13,000円の範囲内です。
オンライン受講も可能になっており、1日講習を受けた後の試験に合格することで受講証明書が発行される流れになっています。講習は基本的に月1〜2回程度の開催で、人気の日程はすぐに満席になってしまうため、早めの予約が重要です。
受講証明書は申請書類の必須項目となるため、申請スケジュールから逆算して講習の予約を取ることをおすすめします。
法人設立費用と個人事業主の場合の費用比較
法人設立の場合は10-25万円(代行依頼時は30万円程度)の登記費用が追加で必要になります。個人事業主の場合は法人設立費用は不要ですが、資産要件の計算方法が異なってくる点に注意が必要です。
法人設立を自分で行う場合は定款作成、公証人による認証、法務局での登記といった手続きが必要で、最低でも10万円程度の費用がかかります。司法書士に代行を依頼する場合は20-30万円程度の報酬が加算されることになります。個人事業主として申請する場合は、住宅ローンなどの個人的な負債も財産要件の計算に含まれるため、法人よりも資産要件を満たすのが困難な場合があります。事業の将来性や税務上のメリットも考慮して、法人設立か個人事業主かを判断することが大切です。
オフィス準備費用とレンタルオフィスの活用比較
一般的なオフィス賃貸の初期費用(敷金礼金・内装工事等)とレンタルオフィス利用時の費用を比較してみましょう。
通常の賃貸オフィスの場合、敷金・礼金で家賃の4-6ヶ月分、内装工事で坪単価10-20万円程度が相場となっています。
レンタルオフィスを利用する場合は初期費用を大幅に抑えることができますが、個室確保・鍵付き保管庫設置などの要件を満たす必要がある点は変わりません。レンタルオフィスでも月額5-15万円程度の利用料に加えて、鍵付きキャビネットの設置や個室の利用料が別途発生することがあります。立地条件や設備の充実度によって費用は大きく変わってくるため、事業計画に合わせた選択が重要になってきます。
人材紹介免許の申請手続きと取得までの流れ【期間約3ヶ月】
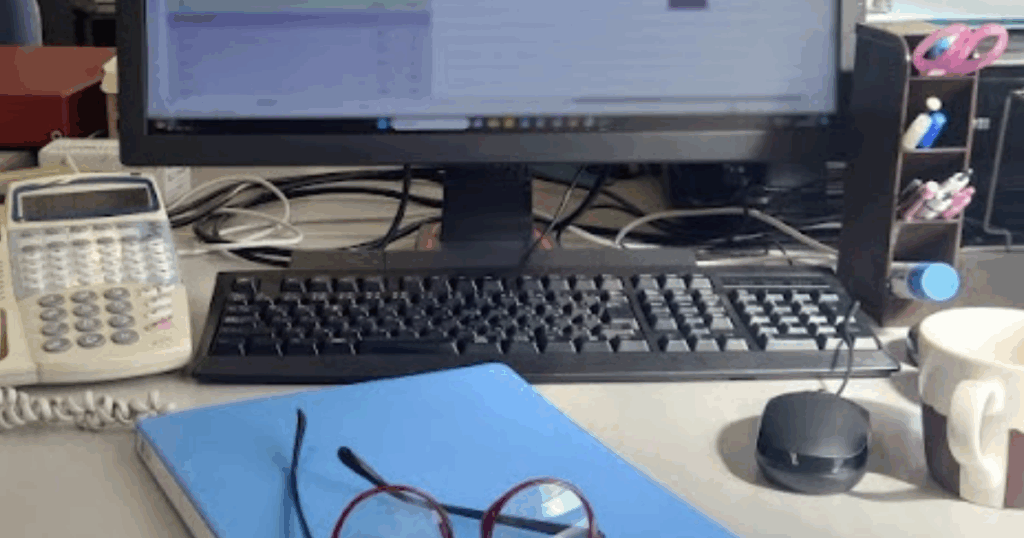
人材紹介免許の申請から許可証交付までは約3ヶ月の期間を要します。この期間中に書類不備が発覚すると再申請が必要となり、さらに時間がかかってしまうため、事前の準備が成功の鍵となります。
| 段階 | 期間目安 | 主な作業内容 |
| 事前準備 | 1-2ヶ月 | 事業所確保、講習受講、書類準備 |
| 申請・審査 | 2ヶ月 | 書類提出、労働局での審査 |
| 許可証交付 | 毎月1日 | 許可証の発行・事業開始 |
全体のスケジュール管理をしっかりと行うことで、予定通りの事業開始が可能になります。
申請前の準備:事業所確保・職業紹介責任者講習受講
事業所の賃貸借契約締結、レイアウト設計、職業紹介責任者講習の受講予約と受講が事前準備として必要になります。
講習は月1-2回程度の開催で予約が必要なため、スケジュールの調整を含めて計画的な準備が求められます。事業所については要件を満たす物件探しから始まり、契約条件の交渉、レイアウト設計まで時間がかかる場合があります。
特に都市部では条件に合う物件が限られているため、複数の選択肢を検討しておくことをおすすめします。職業紹介責任者講習は受講証明書の発行に時間がかかる場合があるので、申請予定日から逆算して早めに受講しておくことが大切です。
申請書類の作成と提出:都道府県労働局経由
管轄の都道府県労働局への書類提出が必要で、事前相談や説明会参加を強くおすすめします。労働局では定期的に説明会を開催しており、申請のポイントや注意事項について詳しく説明してもらえます。
申請書類一式の作成には専門知識が必要な部分も多く、社労士への代行依頼も選択肢として検討するのも良いでしょう。
自分で申請書類を作成する場合は、労働局の担当者との事前相談を活用し、不明な点は遠慮なく質問することが重要です。書類の記載内容に不整合があると審査が長引く原因となるため、提出前の最終チェックは入念に行う必要があります。
審査期間と許可証交付までのスケジュール:毎月1日付与
申請から約2ヶ月の審査期間を経て、毎月1日付で許可証が交付される仕組みになっています。例えば、3月15日に申請した場合、審査完了が5月中旬でも許可証の交付は6月1日となります。
書類不備や要件不足の場合は再申請が必要で、さらに2ヶ月の期間を要する可能性があります。審査期間中に労働局から追加書類の提出や説明を求められることもあるため、連絡に対しては迅速に対応することが大切です。
許可証が交付されるまでは一切の営業活動ができないため、事業開始のタイミングを見据えた申請スケジュールを組むことが重要になってきます。
免許取得後の更新手続き:5年ごと・手数料18,000円
許可の有効期間は5年間で、期間満了前に更新申請が必要です。更新手数料は18,000円で、新規申請時ほど詳細な書類は不要ですが、事業実績や財産状況の報告は求められます。
更新申請は期間満了の3ヶ月前から受け付けており、忘れずに手続きを行うことが重要です。更新を忘れて許可が失効してしまうと、再度新規申請からやり直しになってしまうため、カレンダーに記入するなどして管理することをおすすめします。
更新時には過去5年間の事業実績や法令遵守状況も審査対象となるため、日常的な記録管理も行うようにしましょう。
人材紹介免許に必要な書類一覧と作成のポイント
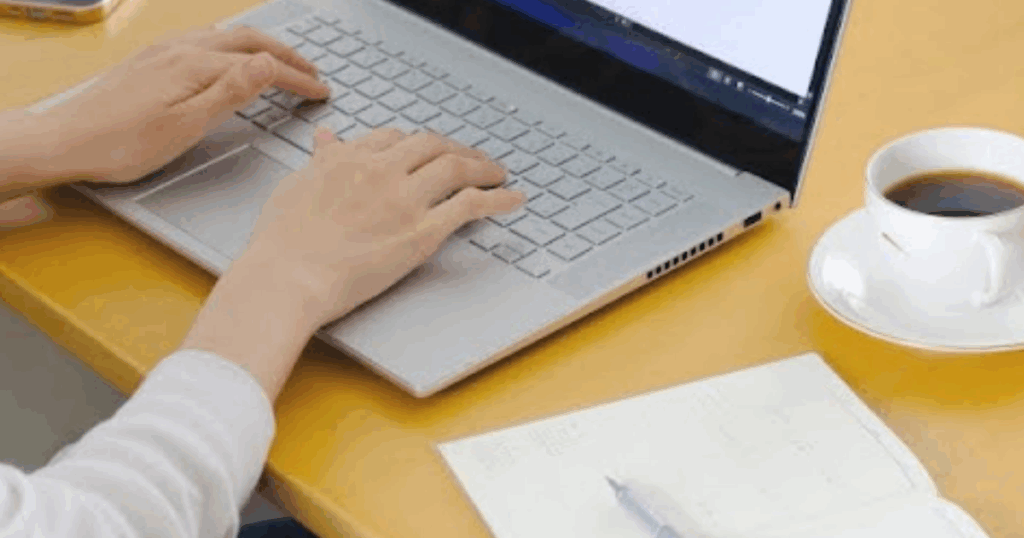
申請に必要な書類は多岐にわたり、それぞれに作成時の注意点があります。書類不備は申請遅延の最大の原因となるため、チェックリストを作成して漏れのないよう準備することが重要です。各書類には有効期限や記載要件があるため、実務的な観点からポイントをお伝えします。
申請書類と添付書類
有料職業紹介事業許可申請書、定款、登記事項証明書、財務諸表等の必要書類の準備が必要です。申請書は厚生労働省の指定様式を使用し、記載漏れや誤記がないよう注意深く作成しましょう。
東京労働局の例:
定款は法人設立時のものが基本ですが、事業目的に職業紹介事業を含める必要があります。
財務諸表については、法人の場合は直近の決算書、個人事業主の場合は確定申告書が必要です。添付書類の中には取得に時間がかかるものもあるため、早めに準備するようにしましょう。
事業所のレイアウト図作成
面談スペース、職業紹介責任者席、鍵付き保管庫の配置を明記したレイアウト図の作成が必要です。PowerPointやExcelなどの簡易ツールでも作成可能ですが、要件を満たす設備の配置が正確に表現されていることが重要です。
レイアウト図には面積の表示、各設備の寸法、プライバシー保護の配慮などを記載する必要があります。面談スペースは求職者との相談内容が他の人に聞こえない構造になっていることが重要で、パーティションや個室の設置状況を明確に示しましょう。
財産要件を証明する書類の準備方法
法人の場合は決算書・貸借対照表、個人の場合は確定申告書・預金残高証明書等の準備が必要です。これらの書類は申請前3ヶ月以内に作成または取得されたものである必要があります。
資産計算の対象となる項目と除外される項目を明確に把握し、要件を満たしているかの確認作業が重要になります。法人の場合、資産には現金・預金、売掛金、固定資産などが含まれ、負債には借入金、買掛金、未払金などが含まれます。個人事業主の場合は、事業用資産と個人資産を区別する必要があり、住宅ローンなどの個人的な負債も計算に含まれるため注意が必要です。
人材紹介免許申請でよくある失敗例

実際の申請では、準備不足や認識不足による失敗が頻繁に発生しています。申請遅延や不許可を防ぐための実践的なアドバイスを、実際の事例を交えながらお伝えします。
財産要件で勘違いをする
「現金500万円があれば大丈夫」という誤解や、負債計算の見落とし、個人事業主の住宅ローン処理の間違いがよく見られる失敗例です。実際には純資産500万円と現金150万円の両方が必要で、負債も含めた正確な計算が求められます。
特に個人事業主の場合、「事業用の資金は十分あるから問題ない」と考えていても、住宅ローンの残債が多額にある場合は純資産要件を満たさない可能性があります。法人の場合でも、設立したばかりで決算期を迎えていない場合の資産計算方法を間違えるケースが見られます。
財産要件の計算は複雑な部分があるため、不安な場合は税理士や社労士に相談することをおすすめします。また、要件を満たすために借入を行う場合は、その借入金も負債として計上されることを忘れてはいけません。
オフィス要件で審査に落ちる
開放的なオープンオフィスでプライバシー保護が不十分、他法人との同居、適切な面談スペースの未確保といった失敗例が多く見られます。「おしゃれなコワーキングスペースで開業したい」と考える方もいますが、個人情報保護の観点から厳しい制限があります。
レンタルオフィスを利用する場合でも、完全個室の確保と独立性の確保が必要で、他の利用者と共有スペースが多い場合は要件を満たさない可能性があります。
事業所選びの段階で労働局に相談し、要件を満たしているかを確認してもらうことで、後のトラブルを避けることができます。
書類不備によって申請が遅延する
添付書類の期限切れ、記載内容の不整合、必要書類の不足といった書類不備が申請遅延の最大の原因です。特に複数の書類間で記載内容に矛盾がある場合は、審査が大幅に遅れることがあります。
よくある不備としては、定款の事業目的と申請書の事業内容が一致していない、財務諸表の数字と資産計算書の数字が合わない、レイアウト図と実際の事業所の構造が異なるといったケースがあります。
申請前に書類チェックリストを作成し、第三者にも確認してもらうことで不備を防ぐことができます。社労士への代行依頼(10-15万円程度)も選択肢の一つですが、費用を抑えたい場合は労働局の事前相談を積極的に活用することがおすすめです。
まとめ
人材紹介免許の取得は決して簡単ではありませんが、正しい知識と十分な準備があれば必ず取得できます。2025年の法改正で新たな規制も追加されているため、最新の情報に基づいた準備が重要です。
費用は最低14万円から、期間は約3ヶ月を要するので、事業開始予定日から逆算したスケジュール管理が成功の鍵となります。特に財産要件、事業所要件、書類準備については入念な確認を行い、不安な点は労働局や専門家に相談することがおすすめです。
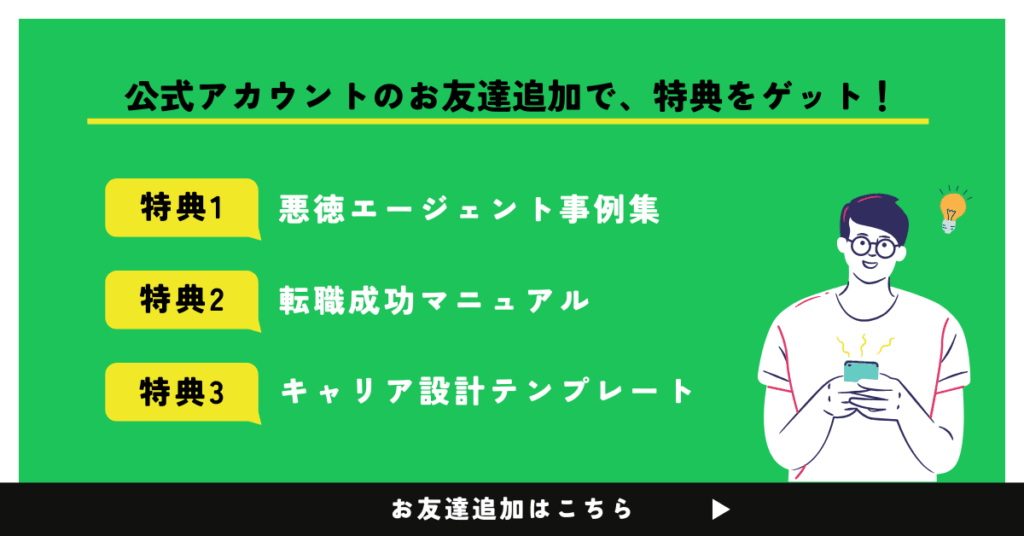
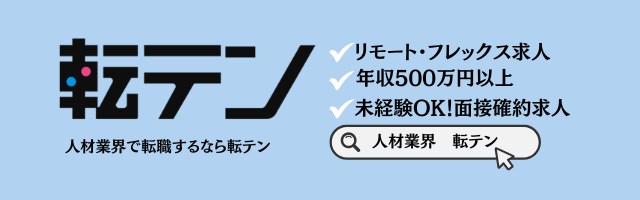

キャリアアドバイザー、リクルーティングアドバイザー、社内人事などを経て、現在は転職メディア「転テン」の運営を担当。転職に悩む方の力になるべく、リアルな現場経験を活かしたノウハウを発信中。あなたの「キャリアづくり」を応援します。
 コンテンツへ移動
コンテンツへ移動

