日々、さまざまな理由から転職を試みる人がいます。「今の仕事に不満がある」「もっと成長できる職場に行きたい」といった、意欲や自身の将来性を加味して決めることも多いです。
しかし、「一度入社した職場は3年は続けた方がいい」、このような言葉を耳にしたことはないでしょうか。実際、「とりあえず3年説」は不透明なところが多く、明確な定めはないので必ずしも受け入れる必要はありません。
そこで今回、本記事ではなぜ入社した職場を3年は辞めてはならないのかはもちろん、居続けた場合のメリット・デメリットなどを紹介していきます。
最後まで読むことで、転職する際の判断材料にもなるため、ぜひご覧ください。
▼いつ転職したらいいのか迷っている方は転職のベストタイミングはいつ?時期・状況・年齢別で徹底解説の記事で確認しましょう。
▼退職を円滑に進めたい方は【完全解説】退職理由の上手な伝え方とは?円満退職の方法や転職面接での回答例文まで徹底解説の記事で確認しましょう。
目次
とりあえず3年と言われる理由

ここでは、なぜとりあえず3年は辞めるなと言われるのか、を紹介していきます。
退職・転職理由は人それぞれですし、現代ではあまり耳にすることはありませんが、なぜ一度入社した職場は3年間は辞められないのでしょうか。
その理由について、以下のようなことが挙げられます。
- 石の上にも3年というマインドがあるから
- 仕事のスキルが身に付くのは3年目から
- 会社に貢献できるタイミングが訪れるのも3年目から
あまり聞くことは少なくなってきましたが「石の上にも3年」といったマインドが残る会社は今でも多いです。
そもそも石の上にも3年は有名なことわざの1つで、今は辛くても耐え続けることで良いことが起こるとされる意味があります。
かつては、実力主義の会社が多数存在し、仕事は見て覚えることが当たり前の時代でした。3年も続けることができれば、中堅社員として会社に重宝される立場になれる年数になるため、下積み時代にさまざまなことを覚えることで成長するとされていました。
つまり、1〜2年目は社会人としての忍耐や精神面を鍛える期間とされており、3年目からがやっと会社の仲間として活躍できる一人前になれるのです。
そのため、とりあえず3年は辞められない文化が今も残っています。
入社して3年以内で退職したいと思う理由5選
ここでは、「入社した職場を3年で辞めたくなってしまう理由」を紹介していきます。
石の上にも3年と言っても、転職できる回数、年齢には制限がありますし、何かしらの事情で退職を余儀なくされることもあります。
3年で退職したいと思う理由には、主に以下のことがありました。
- ブラック企業だったとき
- 職場環境が合わなかったとき
- 成長ややりがいを感じられないとき
- 特別な理由があったとき
- どうしてもやりたい仕事を見つけたとき
ブラック企業だったとき
1つ目の理由は、入社した会社がブラック企業だったときです。
目標以上のノルマやパワハラが日常的に行われ、肉体的にきつく、精神を病んでしまう上に収入が少ない会社がブラック企業の特徴の一つとしてあります。
ほとんどの場合、面接時や説明会の段階では表には出さないので、実際に入社してみないことには分からないといった問題も抱えています。
誤って入社してしまえば、「精神面」や「肉体面」をすり減らしながら日々、業務をこなさなければなりません。
社員の教育上、注意したり叱ったりすることはもちろんあると思いますが、怒号や罵声は教育の範疇を超える行為です。
最悪の場合は、うつ病など社会復帰が難しくなるリスクを抱えていますし、なかなか耐えられるものではないため、3年待たずに退職する人もいます。
職場環境が合わなかったとき
2つ目は、職場の環境に合わなかったときです。
仕事に関してもですが、職場環境の良し悪しは実際に入社してみないことには分かりません。
どんな仕事にも向き・不向きといったものは必ず存在しますし、就活時・面接時までは自分の力量や得意なことを把握しているものでしょう。
しかし、実際に入社して仕事をしてみると「思っていた業務と違う」「成果や実績を残せない」など、活躍できないこともあります。
また、人間関係の構築も社会では必要なことです。
会社といった狭い空間の中では思うようにコミュニケーションが取れず、悩み苦労することもあります。
そのため、職場環境が肌に合わず、3年以内に転職を考えてしまう人も多いです。
成長ややりがいを感じられないとき
3つ目は、成長ややりがいを感じられなかったときです。
人によって違いはありますが、自分のなかで仕事に対し何かしらの「条件」や「期待」といったものはあります。
入社して新人という立場ではなくなり、ある程度仕事を任せてもらえるようになっても、裁量ある業務を任せてもらえないことがあります。
その背景には、入社してから3年目までは、一種の教育期間として定めている企業もあり、新人といった扱いではないにしろ半人前としていることもあるのです。
評価こそされてもキャリアアップに繋がらない場合もあるでしょう。
そのため、成長意欲がある人は、会社の規則や評価基準に納得できず、自身の能力を最大限に活かせる職場を目指すため、退職を考えるようになります。
特別な理由があったとき
4つ目は、特別な理由がある場合です。
せっかく入社した会社を何かしらの特別な理由があり、辞めなければならない事態に陥ってしまうことも少なくはありません。
特別な理由とは、「身内の不幸があって」や「働けなくなる病気が見つかった」など、いわゆる一身上の都合によるものとなります。
前途のような事情はほんの一部ですが、3年を待たずに辞めるための理由としては、十分説得力がありますし、将来的にも重要なことです。
もちろん、それでも生活面や今後のことを考えて、働き続けるといった選択もあるでしょう。
しかし、仕事を取るか何かしらの特別な理由を取るかと天秤にかけたときに、退職を選択する人もいます。
どうしてもやりたい仕事を見つけたとき
最後は、今の仕事よりも自分に合ったやりたい仕事を見つけたときです。
どうしてもやりたい仕事が見つかるといった出会いを経験した人も、中にはいると思います。
長い人生でいつどんなときに、本当にやりたい仕事が見つかるかは分かりません。
また、1つの会社に一生居続けることが必ずしも正しいとは限りませんし、現職でキャリアアップし、上を目指すことも大切なことです。
しかし、視野を広く持ちさまざまな経験をすることも社会では重要なことと言えるでしょう。
「もっと成長したい」「今よりもスキルを身につけたい」など、やりたい仕事を見つけ転職することが、自分の人生に必要なこととして、3年以内に退職を試みる人も多く居ます。
職場に3年以上居続けるメリット

ここでは、「3年以上職場に居続けたとき」のメリットを紹介していきます。
3年待たずに職場を辞める理由は、さまざまなものがありましたが、逆に居続けた場合、どんなメリットがあるのか、以下のようなものがありました。
- 社会人としての経験が得られる
- 能力やスキルを身につけられる
- やりがいや続けたいという意識が芽生える
社会人としての経験が得られる
新卒の社会人は、右も左も分からず社会経験があまりない状態です。
「アルバイト」や「インターン」などで、仕事の経験はあると思いますが、学校から会社といった組織で働くことの意味は大きく違いがあります。
初めて企業に務めることは、それだけで大きな経験で業務を通じて成長していくものです。
また、新卒は言わずもがな、中途で入社したとしても社会人の経験を得られるチャンスがあります。
中途とはいえど、完璧な存在ではありませんし、社会は常に進化するので新たなことを学ぶためにも居続けることで得をすることがあるでしょう。
しかし、転職をすることで、新たな経験を得られ成長できることは事実ですが、現職の会社とともに自身も成長することも貴重な体験です。
もちろん、転職が悪いことではありませんが、現職でしっかりと経験を得ることも社会人にとっては大切なことになります。
能力やスキルを身につけられる
どんな仕事でもやり方次第で、自身の成長につながる能力やスキルを習得することは可能です。
ブラック企業で、精神や肉体を壊してまで居続ける必要はありませんが、そのような事情が特になく、問題のない会社であれば居続けることで得を積むことができます。
得というのは、なにも特別なことではなく業種によって違いはありますが、仕事に必要な「資格」や「技術」を習得できることです。
資格や手に職が付く技術面があるのと、ないのとでは仮に転職を考えて面接に望んだ際の印象も違いますし、自身の価値をアピールすることもできます。
また、能力が上がることで、転職の選択肢の幅も広がりより効率良く、自分に合った仕事を探すこともできるでしょう。
やりがいや続けたいといった意識が芽生える
入社して3年目までは、教育期間として裁量のある仕事を任されず、不平不満が出てくるものです。
毎日、似たような仕事の繰り返しでマンネリ化し、次第にモチベーションも下がってくるでしょう。
ただし、必ずしも3年目までの評価が反映されていないわけではありません。
ブラック企業はまた別ですが、一般的な会社はしっかりと入社してからの成果や実績を見てくれているものです。
そのため、3年を皮切りにだんだんと裁量のある仕事を任せてもらえる可能性があります。
自分に取っては誇れるような実績ではなくても、真摯に取り組んだ業務に対して評価されることが多くなってくるので、続けたいと思う意識が芽生えるでしょう。
職場に3年以上居続けるデメリット

ここでは、職場に3年以上居続けるデメリットを紹介していきます。
居続けるメリットがある一方で、将来にも関わってくるような重大なデメリットになり得る場合があります。
そのため、以下のことに注意しましょう。
- 第二新卒ではなくなる
- 必要な人材と見られ辞めづらくなる
- 居続けたとしても経験を得られないこともある
第二新卒ではなくなる
新卒で入社した場合、3年以上経ってしまうと第二新卒ではなくなってしまいます。
企業に入社する人は、「新卒・第二新卒・中途」などの分類に分けられ、採用の基準として見られることがあります。
その中でも第二新卒は、新卒と中途の間に位置し、明確な定めはなく企業によって定義が変わりますが、2年〜3年と設定されていることがほとんどです。
新卒よりも社会経験があり、中途よりもまだ前職に染まりきっておらず、ある程度即戦力として見込める人材が第二新卒の立ち位置となります。
第二新卒だからといって採用が確実に保証されるわけではありませんが、企業によっては新卒・中途よりも欲している人材です。
しかし、3年を超えてしまうとほとんどの企業が中途として見る傾向にあるため、第二新卒としてのメリットがなくなってしまいます。
必要な人材として見られ辞めづらくなる
3年も同じ職場に居続けると当然、勤めている会社の内部事情や業務の仕方などをかなり理解している中堅社員となります。
新人や部下の育成、管理を任される立場になりますが、期待されてしまっているがゆえに「辞めさせてもらえない」事態が発生してしまう可能性があるでしょう。
さまざまな裁量のある仕事を任されることは、会社がそれだけ成長してほしいといった期待がある証拠です。
しかし、必要な人材とされることは非常に有り難いことですが、過度な「成長」や「キャリアアップ」の期待は、ときにモチベーション低下の原因となります。
そこまで大きな仕事は望まず、一般社員のままで仕事がしたいと思っている人にとっては、十分に転職のきっかけになるものです。
居続けたとしても経験を得られないこともある
最初に入社した職場に3年以上居続けたとしても、たいして経験を得られない場合があります。
社会人としての経験は得られますが、例えば他の仕事にも活用できる資格やスキルにあまりこだわりがない企業では習得は厳しいです。
また、ブラック企業である場合は、精神面の強化はできる可能性がありますが、逆に社会復帰が難しくなるほどのダメージを受ける場合もあります。
活かせる資格やスキルがないと、転職時のアピールにはなりにくいですし、異業種への転職が厳しくなってしまうでしょう。
しかし、職場内でのコミュニケーションや部下の管理など、能力を高める機会は少なからずあるので、経験を得られる機会を自ら増やすことが大切です。
▼自分に合った転職先を見つけたい方は転職先の選び方は?後悔しない企業選びの基準と成功するための方法を徹底解説の記事で確認しましょう。
職場で3年を待つべきか転職すべきかの判断基準

ここでは、3年待った方が良いのか、転職すべきかの基準を紹介していきます。
さまざまな理由から転職するべきか、3年は修行期間として耐えるべきかと悩むことがあるでしょう。
そこで、判断基準として以下のことを抜粋しました。
- なぜ今の職場を辞めたいのか
- 現職を辞めることが正解なのか
- 転職しないと解決できないことか
石の上にも3年と言うことわざがあるように、耐えて努力し仕事をすることは大切です。
長く続けることで、会社の内部事情や本当の意味で仕事のやり方を理解でき、3年未満の退職者よりも転職時に良い印象を与えることができます。
また、裁量のある仕事を任せてもらい、正当に評価されることでスキル・キャリアアップの機会に恵まれる可能性も増えてきます。
しかし、前途にもあった「仕方のない事情」や「ブラック企業」だった場合は、その限りではありません。
第二新卒や年齢問題もあるため、時期やチャンスを逃してしまうと希望条件での転職ができない可能性があるでしょう。
そのため、自身のキャリアプランや将来のことを良く考えて、慎重に行動することが大切です。
自分に合ったキャリアの選択に必要な行動

ここでは、転職するために必要な行動を紹介していきます。
とりあえず3年の壁を気にせず居続けたり、職場を離れる決断をしたとしても以下のことに注意しなければなりません。
- 必要な経験を蓄える
- 明確な転職目標を決める
- スキルや経験の棚卸しをする
まず、大前提として明確な転職目標を決めましょう。
「条件・環境・仕事内容」などといった明確な転職目標は、自分に合った職場を見つけるための重要事項です。
準備せずに何もない状態で転職を試みても失敗してしまうこともあり、その分居続けてしまうことにもなります。
また、自分は何が得意で不得意なのか、スキルや経験の棚卸しをすることも必要となり、足りないものがあれば現職で補い、行動する時期を見定めることも選択の一つです。
先を見据え、しっかりとしたキャリアを築き上げたいのであれば、焦らず慎重に行うことが重要となるでしょう。
まとめ

とりあえず3年は職場に残るという説は、必ずしも正しいとは限りませんでした。
確かに、3年残ることで仕事に対しての「知見」や「技術」が身につくなどのメリットがあります。
また、中堅社員として職場の雰囲気にも慣れたり、円滑なコミュニケーションが取れるようになったりと悪いことだけではありません。
しかし、新卒で入社すれば第二新卒ではなくなる可能性がありますし、思った仕事と違ったなどのミスマッチが原因でストレスを感じることもあります。
そのため、積極的に仕事に取り組むなどして、経験や知見を深め、必要であれば自身でスキルや能力の習得を目指してから転職するかを考えることが重要になるでしょう。
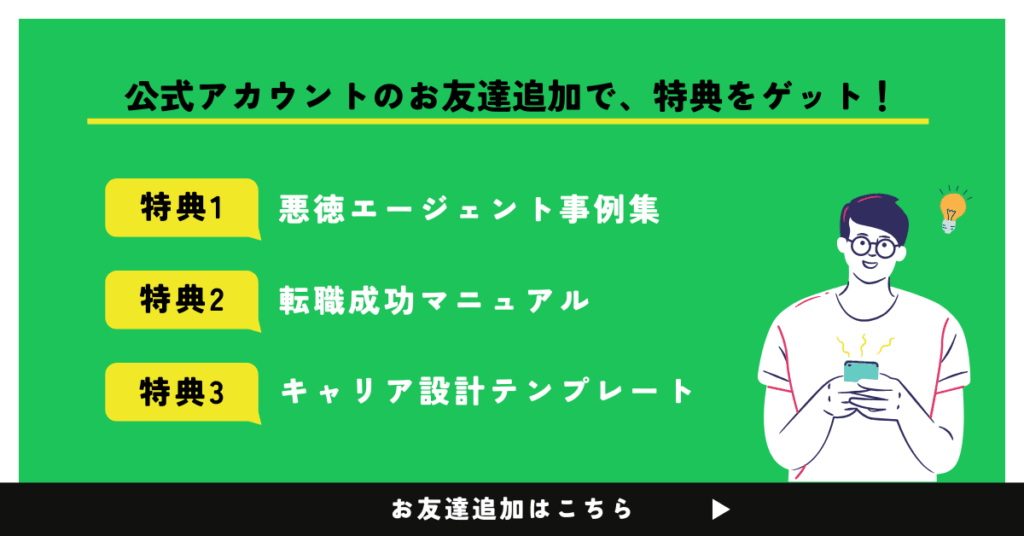
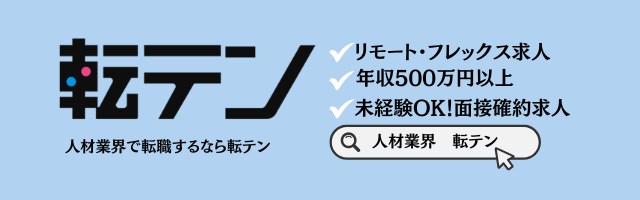

キャリアアドバイザー、リクルーティングアドバイザー、社内人事などを経て、現在は転職メディア「転テン」の運営を担当。転職に悩む方の力になるべく、リアルな現場経験を活かしたノウハウを発信中。あなたの「キャリアづくり」を応援します。
 コンテンツへ移動
コンテンツへ移動

