第二新卒として転職を考えているものの、「いつまで第二新卒として扱われるのか」という疑問を抱く方は多いでしょう。企業によって第二新卒の定義は異なり、年齢や卒業年度、社会人経験年数など複数の基準が存在します。
本記事では、2025年現在の第二新卒の定義を詳しく解説し、卒業年度別の転職戦略やメリット・デメリットまで包括的にお伝えします。適切なタイミングで転職活動を進めることで、キャリアアップの可能性を最大化できるでしょう。
目次
第二新卒の定義と「いつまで」の基準

第二新卒の定義は企業や業界によって幅があるものの、一般的には新卒入社後1~3年以内の転職希望者を指します。年齢では25歳~27歳が上限とされることが多く、社会人経験年数や卒業年度によっても判断基準が変わります。
第二新卒の基本的な判断基準
| 判断基準 | 一般的な目安 | 企業による違い | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 25歳~27歳まで | 28歳~29歳まで認める企業も | 学歴により上限が変動 |
| 社会人経験年数 | 1年~3年以内 | 5年程度まで認める場合も | 職務経験の質も重要 |
| 卒業年度 | 卒業後3年以内 | 企業により柔軟に対応 | 2025年現在は22卒~24卒が主流 |
| 転職回数 | 1回目の転職 | 複数回でも可能な場合も | 転職理由の一貫性が重要 |
ここでは、各種基準を詳しく解説していきます。
一般的な第二新卒の定義
第二新卒は、新卒として入社した企業を1~3年以内に退職し、転職を希望する人材を指します。新卒採用とは異なり、社会人としての基本的なマナーやビジネススキルを身に付けているものの、まだ特定の業界や職種に深く専門化していない段階の人材として位置づけられています。
企業側にとって第二新卒は、新卒採用のような教育コストを抑えながら、若手人材を確保できる魅力的な採用対象です。一方で、転職者にとっては新卒時の企業選びの反省を活かし、より自分に合った職場環境や業界を選択する機会となります。
年齢による第二新卒の判断基準
年齢による第二新卒の判断基準は、学歴によって異なります。大卒者の場合、22歳で新卒入社し、25歳頃までが第二新卒として扱われるのが一般的です。大学院修了者は24歳で新卒入社するため、27歳頃まで第二新卒として認められることが多くなります。
高校卒業者の場合、18歳で就職し、21歳頃までが第二新卒の対象年齢となります。ただし、高卒の場合は企業によって判断基準にばらつきがあり、専門学校卒業者についても同様の扱いを受けることが多いです。
年齢の上限については、企業の採用方針や業界の特性によって柔軟に運用されており、28歳や29歳でも第二新卒として扱う企業も存在します。
社会人経験年数による判断基準
社会人経験年数による第二新卒の判断では、1年未満から3年以内が主流となっています。入社1年未満での転職は「早期離職」として懸念されることもありますが、明確なキャリアビジョンがあれば第二新卒として受け入れられる場合も多いです。
2年から3年の経験を持つ人材は、基本的なビジネススキルを習得し、一定の職務経験を積んでいることから、企業からの評価も高くなる傾向があります。一部の企業では、5年程度の経験者まで第二新卒として扱うケースもありますが、これは業界や職種によって大きく異なります。
職務経験の質も重要な判断要素となり、単純に年数だけでなく、どのような業務に携わり、どの程度のスキルを身に付けたかが評価の対象となります。
卒業年度別の第二新卒該当基準
2025年現在の状況を踏まえ、各卒業年度の第二新卒該当状況を整理します。
2024年卒業の24卒は入社1年目から2年目にあたり、最も第二新卒として扱われやすい時期です。2023年卒業の23卒は入社2年目から3年目で、経験とポテンシャルのバランスが取れた魅力的な人材として評価されます。
2022年卒業の22卒は入社3年目から4年目にあたり、第二新卒期間の終盤に位置します。企業によっては中途採用として扱われることもありますが、まだ第二新卒として認められる可能性があります。2021年卒業以前の人材については、基本的に中途採用として扱われることが多くなります。
院卒・高卒別の判断基準
大学院卒業者の場合、一般的に24歳で新卒入社するため、27歳頃まで第二新卒として扱われることが多いです。修士課程修了者と博士課程修了者では年齢が異なりますが、企業側は専門性の高さと若手としてのポテンシャルを評価する傾向があります。
高校卒業者については、18歳での就職が一般的なため、21歳頃までが第二新卒の対象となります。ただし、高卒者の場合は企業の採用方針による違いが大きく、一部の企業では年齢よりも実務経験を重視することもあります。
企業によっては、学歴に関係なく「卒業後3年以内」という統一基準を設けている場合もあり、個別の採用要項を確認することが重要です。また、専門学校卒業者についても、高卒者と同様の扱いを受けることが一般的ですが、取得した資格や専門性によって評価が変わることもあります。
【2025年版】卒業年度別:第二新卒該当状況と転職戦略

2025年現在の転職市場において、各卒業年度の第二新卒該当状況と効果的な転職戦略を詳しく解説します。卒業年度によって転職市場での立ち位置や企業からの期待値が異なるため、それぞれに適した転職アプローチを理解することが成功の鍵となります。
24卒(2024年卒業)
2024年卒業の24卒は、現在入社1年目から2年目にあたり、第二新卒として最も注目される年代です。基本的なビジネスマナーを身に付けながらも、まだ特定の業界や職種に固執していない柔軟性が評価されます。
転職市場での状況
- 現在の状況:入社1年目~2年目
- 転職市場での評価:若手として高い注目度
- 最適な転職時期:入社1年経過後の春~夏
- 注意点:短期離職への懸念
転職を検討する理由として、入社前のイメージと実際の業務内容のギャップや、キャリアビジョンの明確化が挙げられることが多いです。最適な転職時期として、入社1年が経過した春頃から夏にかけてが推奨されます。この時期であれば、一定の社会人経験を積んだことを証明でき、同時に新しい環境での成長意欲をアピールできます。
注意すべきポイントとして、短期間での離職に対する企業の懸念を払拭する必要があります。転職理由を明確にし、次の職場では長期的にキャリアを積む意思があることを強調することが重要です。
23卒(2023年卒業)
2023年卒業の23卒は、入社2年目から3年目にあたり、第二新卒として最も価値の高い時期を迎えています。基本的なビジネススキルを習得し、一定の職務経験を積んでいることから、企業からの評価も高くなります。
転職市場での状況
- 現在の状況:入社2年目~3年目
- 転職市場での評価:第二新卒の黄金期
- 最適な転職時期:通年で良好なタイミング
- 注意点:高い期待値への対応
この時期の転職は、キャリアアップや専門性の向上を目的とすることが多く、より戦略的なアプローチが可能です。転職市場での評価として、実務経験に基づく具体的な成果や学びをアピールできる点が強みとなります。プロジェクトの遂行経験や、チームでの協働経験など、新卒では語れない実践的なエピソードを持っていることが差別化要因となるでしょう。
スキルアップのポイントとして、現職での経験を体系化し、転職先で活かせる能力として整理することが重要です。業界知識、技術スキル、コミュニケーション能力など、多角的な視点から自分の価値を見直しましょう。
22卒(2022年卒業)
2022年卒業の22卒は、入社3年目から4年目にあたり、第二新卒期間の終盤に位置します。この時期になると、企業によっては中途採用として扱われることもありますが、まだ若手人材としての価値は十分に認められています。
転職市場での状況
- 現在の状況:入社3年目~4年目
- 転職市場での評価:第二新卒期間の終盤
- 最適な転職時期:早めの行動が推奨
- 注意点:中途採用扱いの可能性
3年間の実務経験により、一定の専門性を身に付けていることが期待されます。中途採用との違いとして、22卒はまだ成長ポテンシャルを重視される傾向があります。
一方で、即戦力としての期待も高まるため、これまでの経験をどう活かし、どのような価値を提供できるかを具体的に示す必要があります。
経験を活かした転職方法として、これまでの職務経験を棚卸しし、転職先の業界や職種に応じてアピールポイントを調整することが重要です。リーダーシップ経験や、困難なプロジェクトの遂行経験など、3年間で培った実績を前面に押し出しましょう。
21卒以前
2021年卒業以前の人材については、基本的に中途採用として扱われることが多くなります。ただし、企業によっては柔軟な基準を設けており、第二新卒として扱われる可能性もあります。
転職市場での状況
- 現在の状況:入社4年目以降
- 転職市場での評価:中途採用が基本
- 最適な転職時期:企業方針次第
- 注意点:第二新卒扱いは限定的
この場合、年齢や経験年数よりも、個人の成長ポテンシャルや転職理由が重視される傾向があります。中途採用扱いとなることが多いため、即戦力としての能力やスキルが重要な評価要素となります。これまでの職務経験で培った専門性や、実績を具体的な数値で示すことが求められます。
企業により判断基準が異なるため、志望企業の採用方針を事前に調査し、第二新卒として扱われる可能性があるかどうかを確認することが重要です。また、転職エージェントを活用し、個別の企業情報を収集することも効果的です。
第二新卒で転職するメリット・デメリット

第二新卒での転職は、キャリア形成において重要な転換点となります。新卒採用とは異なる立ち位置にありながら、中途採用ほどの高いスキル要件を求められないという独特のポジションから、様々なメリットとデメリットが存在します。
第二新卒転職の特徴比較
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| キャリアチェンジ | 異業種・異職種に挑戦しやすい | 年収ダウンのリスク |
| 企業選び | 社会人経験を活かした現実的な判断 | 「すぐ辞める人」という懸念 |
| 選考プロセス | 比較的短期間での転職活動 | 即戦力期待による負荷 |
| 成長性 | ポテンシャル重視の評価 | 専門性の不足 |
これらの特徴を理解し、適切な対策を講じることで、第二新卒転職のメリットを最大化し、デメリットを最小化することが可能です。
第二新卒転職の5つのメリット
まずはメリットについて解説していきます。
異業種・異職種へ挑戦しやすい
第二新卒の最大のメリットは、異業種・異職種への転職がしやすいことです。新卒時とは異なり、社会人経験を通じて自分の適性や興味のある分野が明確になっているため、より戦略的なキャリアチェンジが可能です。企業側も、基本的なビジネスマナーを身に付けた人材が新しい分野にチャレンジすることに対して好意的に捉える傾向があります。
IT業界から金融業界へ、営業職からマーケティング職へといった大幅なキャリアチェンジも、第二新卒の時期であれば十分に可能です。特に成長産業や人手不足の業界では、意欲的な第二新卒人材を積極的に受け入れています。
新卒時の反省を活かして企業選びができる
新卒採用時の企業選びでは、企業の知名度や初任給、福利厚生などの表面的な情報に基づいて判断することが多いものです。しかし、第二新卒での転職では、実際の社会人経験を通じて得た知見を活かし、より現実的で自分に適した企業選びが可能になります。
新卒で1~3年も働いていれば、職場の雰囲気、上司との相性、業務内容の具体性、キャリアパスの明確さなど、実際に働いてみなければわからない要素について、より深く検討できるようになっているでしょう。これにより、ミスマッチのリスクを大幅に減らすことができます。
社会人経験を評価してもらえる
第二新卒は、新卒採用とは異なり、実際の社会人経験を持つ人材として評価されます。基本的なビジネスマナー、電話応対、メールの書き方、会議の進め方など、新卒が入社後に習得する基本スキルを既に身に付けていることが大きなアドバンテージとなります。
また、実際の職務経験を通じて身に付けた業界知識や専門スキル、プロジェクト遂行経験なども評価の対象です。これらの経験は、面接での具体的なエピソードとして活用でき、説得力のある自己PRが可能になります。
比較的短期間での転職活動が可能
第二新卒の転職市場は活発で、企業側も積極的に採用を行っているため、比較的短期間での転職活動が可能となります。新卒採用のような長期間にわたる選考プロセスではなく、中途採用と同様のスピード感で進むことが多いです。
転職エージェントや転職サイトでも第二新卒向けの求人が豊富に用意されており、効率的に転職活動を進められる環境が整っています。通常、2~3ヶ月程度で転職先が決定することが多く、長期間の就職活動による精神的負担を軽減できると言えるでしょう。
成長可能性を重視されるため高いスキルレベルを求められない
第二新卒は、即戦力としての能力よりも成長ポテンシャルが重視される傾向があります。企業側は、第二新卒人材に対して高度な専門スキルや豊富な経験を期待しているわけではなく、むしろ学習意欲や適応能力、コミュニケーション能力などの基本的な能力を評価するのです。
これにより、専門性の高いスキルを習得していない場合でも、意欲と基本的な能力があれば転職成功の可能性が高くなります。入社後の教育研修制度も充実している企業が多く、働きながらスキルアップを図ることができるでしょう。
第二新卒転職の注意すべきデメリット
次はデメリットについて解説します。
年収ダウンのリスクがある
第二新卒での転職では、年収がダウンする可能性があります。特に異業種・異職種への転職の場合、新しい分野での経験がないため、現在の年収水準を維持できないことが多いです。また、転職先企業の給与体系や業界の給与水準によっても影響を受けます。
ただし、長期的な視点で考えれば、適切な企業選びと継続的なスキルアップにより、将来的な年収アップの可能性は十分にあります。短期的な年収ダウンよりも、キャリア全体での成長と満足度を重視することが重要です。
「すぐ辞める人」という懸念を持たれるリスクがある
第二新卒の転職では、「またすぐに辞めてしまうのではないか」という企業側の懸念を払拭する必要があります。特に短期間での離職経験がある場合、継続性に対する疑問を持たれることがあるでしょう。
この懸念を解消するためには、転職理由を明確にし、次の職場では長期的にキャリアを積む意思があることを具体的に示すことが重要です。前職での学びや成長、そして転職によって実現したいキャリアビジョンを論理的に説明できるように準備しましょう。
即戦力としての期待をされすぎることがある
企業によっては、第二新卒に対して過度な期待を寄せる場合があります。社会人経験があることから、新卒よりも即戦力としての活躍を期待され、入社直後から高い成果を求められることがあるでしょう。
このような状況に対処するためには、面接段階で自分のスキルレベルや経験を正直に伝え、企業側の期待値を適切に調整することが重要です。また、入社後は積極的に学習し、期待に応えられるよう努力する姿勢を示すことが求められます。
よくある質問と回答(Q&A)

第二新卒の転職に関して、多くの方が抱く疑問や不安について、実際の転職市場の状況を踏まえながら詳しく回答します。これらの情報を参考に、より効果的な転職戦略を立てていただければと思います。
複数回転職していても第二新卒として扱われる?
1回目の転職であれば、ほとんどの企業で第二新卒として扱われます。新卒入社した会社を辞めて初めての転職という状況は、第二新卒の典型的なパターンとして認識されているためです。転職理由が明確で、キャリアビジョンがしっかりしていれば、企業側も前向きに評価してくれるでしょう。
複数回転職歴がある場合の対処法として、各転職の理由を論理的に説明し、一貫したキャリア戦略があることを示すことが重要です。
短期間での転職を繰り返している場合は、中途採用として扱われる可能性が高くなりますが、それぞれの転職で得たスキルや経験を具体的にアピールすることで、プラスの評価を得ることも可能でしょう。
第二新卒での年収アップは可能?
第二新卒での年収アップは可能ですが、現実的には維持または微増程度が一般的です。異業種・異職種への転職の場合は、一時的に年収がダウンすることも珍しくありません。ただし、成長性の高い業界や職種への転職により、中長期的な年収アップの可能性は十分にあります。
現実的な年収水準として、前職の年収を基準に±50万円程度の範囲で考えておくのが妥当でしょう。将来的な昇給の可能性については、転職先企業の成長性、評価制度、昇進の仕組みなどを事前に確認し、長期的なキャリアプランを立てることが重要です。
第二新卒に求められるスキルレベルは?
基本的なビジネスマナーは必須要件として求められます。電話応対、メールの書き方、会議での振る舞い、報告・連絡・相談の仕組みなど、社会人として最低限必要なスキルは身に付けておく必要があるでしょう。これらは新卒採用では入社後に教育される内容ですが、第二新卒では既に習得していることが前提となります。
業界特有のスキル要件については、転職先の業界や職種によって大きく異なります。未経験分野への転職の場合は、その業界の基本的な知識を事前に学習し、学習意欲と適応能力をアピールすることが重要です。経験のある分野であれば、これまでの実務経験で培ったスキルを具体的に整理し、転職先でどのように活用できるかを明確にしておきましょう。
転職活動期間の目安は?
第二新卒の転職活動期間は、平均的に2~3ヶ月程度が目安となります。新卒採用と比較して選考プロセスが短縮されることが多く、効率的に活動を進められる環境が整っていることが多いですが、希望する業界や職種、企業規模によって期間は変動することもあるでしょう。
効率的な進め方として、転職エージェントの活用、複数企業への同時応募、面接対策の徹底などが重要です。また、現職を続けながら転職活動を行う場合は、スケジュール管理に注意し、計画的に進めることが成功の鍵となります。転職理由の整理、自己分析、企業研究などの準備期間も含めて、全体で3~4ヶ月程度を見込んでおくと良いでしょう。
まとめ:第二新卒の期間を最大限活用した転職成功へ
第二新卒の定義は企業によって異なりますが、一般的には新卒入社後1~3年以内、年齢では25~27歳頃までが目安となります。2025年現在、24卒から22卒までが第二新卒の主要な対象層となり、それぞれ異なる転職戦略が必要です。
第二新卒転職の最大のメリットは、異業種・異職種への挑戦がしやすく、新卒時の反省を活かした企業選びができることです。一方で、年収ダウンのリスクや「すぐ辞める人」という懸念を持たれる可能性もあります。
成功のポイントは、自分の卒業年度と経験年数を正確に把握し、それに適した転職戦略を立てることです。転職理由を明確にし、次の職場での長期的なキャリアビジョンを描くことで、企業側の懸念を払拭し、より良い転職結果を得ることができるでしょう。
第二新卒という貴重な期間を最大限活用し、理想のキャリアを実現してください。
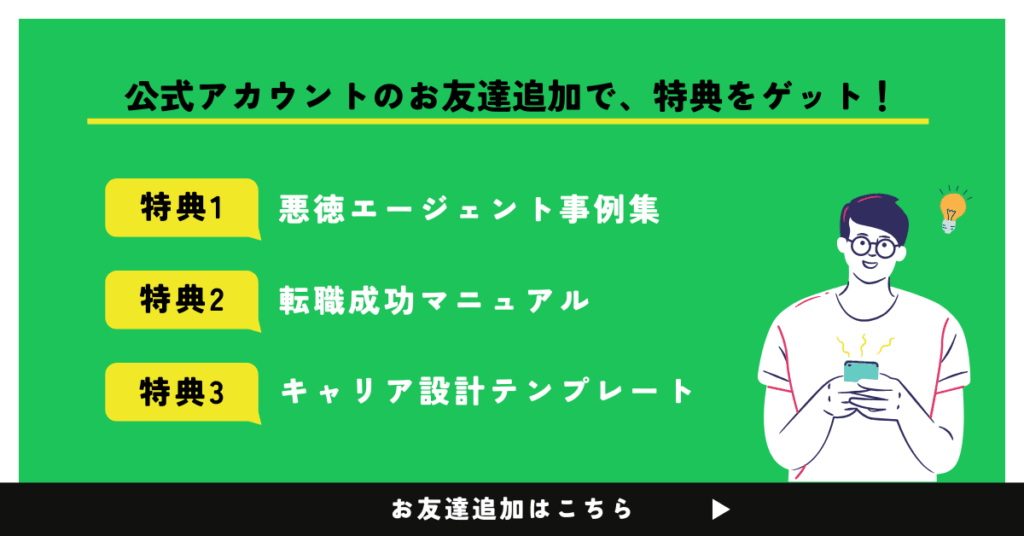
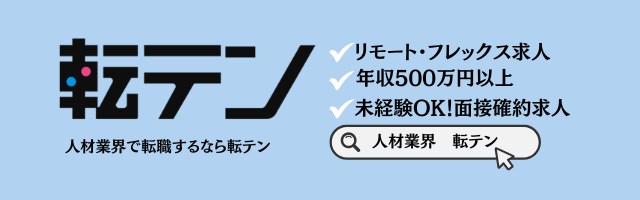

キャリアアドバイザー、リクルーティングアドバイザー、社内人事などを経て、現在は転職メディア「転テン」の運営を担当。転職に悩む方の力になるべく、リアルな現場経験を活かしたノウハウを発信中。あなたの「キャリアづくり」を応援します。
 コンテンツへ移動
コンテンツへ移動

